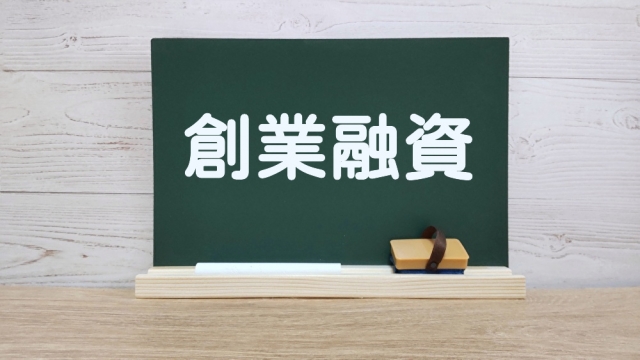現預金月商比率は企業の資金繰り健康度を示し、融資判断に影響します。
現預金月商比率とは
金融機関に融資を申し込む際に決算書や試算表の提出を求められますが、金融機関はどこを見ているのでしょうか?
融資を申し込んできた企業のざっくりとした現状を把握するには現預金月商比率を確認するのが一番早いといわれています。現預金月商比率とは、企業がどれだけ健全な資金繰りを行っているかを示す重要な指標の一つです。この比率は、企業の現金および預金残高を月間の売上高で割ることにより算出されます。通常、この比率が高ければ高いほど、企業には十分なキャッシュが存在し、突発的な支出や経済的な変動にも強いとされます。特に、中小企業や創業間もない企業にとっては、この比率が投資の健全性や融資の信用度を左右する重要な要因として評価されます。現預金月商比率が低すぎる場合、資金繰りの困難さが予想され、融資を受ける際の障壁となることがあります。したがって、企業としては適切な資金管理を行い、この比率を一定水準に保つことが求められます。この指標は、企業が持続可能な経営を続けるために不可欠な要素となり得るため、創業者を始め経営者全般が理解し、日々の経営に活かすべき重要な数字として扱われます。行政書士髙杉忍経営法務事務所では、こうした資金管理の観点からも創業支援を行い、事業計画の策定から実現に至るまでサポートを提供しています。
比率の計算方法
現預金月商比率は、企業の資金繰りを評価する際に重要な指標の一つです。この比率は、企業がどの程度の期間、現預金で月商を賄えるかを示します。計算方法はシンプルで、企業の総現預金を月間売上高で割ることで得られます。具体的には、【現預金額 ÷ 月間売上高】で算出され、この比率が高いほど、企業の資金繰りが良好であると判断されます。
この指標は、融資審査においても非常に重要です。金融機関は、企業が短期間で資金不足に陥らないかを確認するため、現預金月商比率をチェックします。特に新規事業やスタートアップ企業では、資金繰りの安定性は事業成功の鍵となるため、この指標の管理が求められます。理想的には、3ヶ月以上の月商を現預金で持つことが推奨されます。これにより、急な出費や収入減少時でも柔軟に対応でき、経営の安定性を確保することが可能です。
月商は業種、業態や季節性によって幅があるため現預金水準につていも、一括りに月商の何か月分とは判断できないといわれますが、創業間もない経営者はまずは月商の1~3か月分を目安にするべきと考えます。
融資判断への影響
融資判断において、金融機関は企業の返済能力を慎重に評価します。その際、現預金月商比率は重要な指標の一つです。この比率は、企業が毎月の売上に対してどれだけの現預金を保持しているかを示し、資金繰りの余裕度を測る指標とされています。この指標に余裕があると、近年のコロナ禍のように企業が予測外の支出の必要に迫られたときにも対応できると見なされ、融資を受ける際の信用度が増します。金融機関は、この指標をもとに企業が突発的な経済変動にも耐えうるかを判断します。
現預金月商比率は、特に変動の激しい業界や季節的な影響を受けやすい企業にとって重要です。不安定な経済状況下では、資金繰りが悪化しやすいため、現預金が十分であることが融資審査時の安心材料となります。逆に、比率が低い場合は、追加の資金調達の必要性が早期に生じるリスクがあると判断され、融資条件が厳しくなる可能性があります。したがって、この比率を維持し適切な水準に保つことが企業の健全性をアピールするためにも重要です。
また、融資を申請する際には、事業計画書においてこの比率をどのように管理し、維持するかを明確に示すことが求められます。資金繰りの戦略や現金流動性の管理方法が具体的に示されていると、信用度が高まり、金融機関からのサポートを受けやすくなります。札幌創業支援センターでは、このような経営指針の策定をサポートし、金融機関への説明がスムーズに進むよう支援しています。起業家がこの比率を適切に管理し、活用することで、事業の成長と安定がより確実なものとなります。