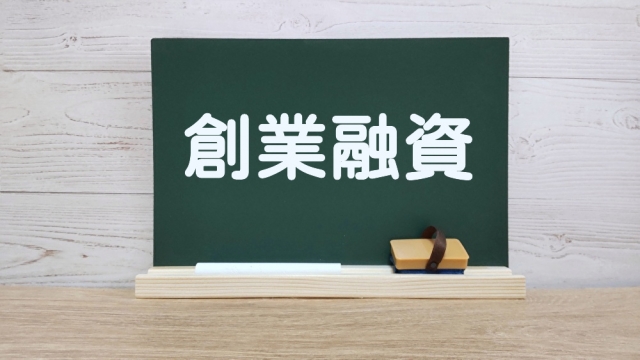前回は、公庫での面談で注意すべきことをお話ししましたが、今回は具体的にどのようなことを訊かれるのかをご説明します。
私の事務所では融資申込み後、面談日程が確定した後再度お客様とポイントの整理と確認を行います。創業計画書自体はお客様と一緒に作成するのですが、それ自体一生の間に何度もある事ではないので、公庫の担当者に準備していなかった事を訊ねられてしどろもどろになって心証を悪くすることを避けるためです。
以下、創業計画書の項目の順に説明します。
1.創業の動機
創業に至った経緯を説明します。
例えば、飲食業の就業経験が長い方なら飲食業での創業、建設業経験のある方なら建設業での創業が自然でしょう。反対に建設業での経験したない方が飲食業で創業したいと融資を申込んでも結果は厳しいものとなるでしょう。
2.代表者の経歴
代表者の最終学歴から、勤務履歴・就業内容を記入します。
融資担当者は過去の経歴からこれから創業しようとする事業とに親和性があるかどうかを検証します。
3.取扱商品・サービス
自社が取扱う商品やサービスはどのようなものか、他社に比べての優位性は何なのか、
なぜその商品を扱うのかが訊かれます。また、物販なら仕入先はどうしてここなのか、仕入条件はどうなっているのかなど事前に確認が必要です。
取扱品目をどのように売っていくのか、ターゲットは何なのかきめ細かい分析が必要です。
4.事業の見通し
創業当初の売上高、仕入高、経費の内訳、利益額と創業後事業が軌道に乗ってからの売上高、仕入高、経費、利益の状態の見通しを記入します。
各項目について面談での説明と整合性があるか、見通しが楽観的すぎないかなどが問われます。
さらに、万が一事業が予定通りに進まなかった場合はどうするのかも訊かれます。
ここで重要なのは自己資金をどれだけ余力をもって準備しているかが重要でしょう。
5.資金の使い道
事業を立ち上げるうえで、何にどれくらいの資金を使うのかを説明します。
具体的には購入する設備の見積りを添付して説明することになります。
過去にあった事例ですが、パソコンの見積りで価格とスペックが見合わない見積りがありました。同スペックのパソコンなら安いところで購入すべきでしょうし、それでも購入するのであれば何かメリットがあるのか(ソフトウエアのサービスがあるとか)ぐらいは説明できるようにしなければなりません。
また、運転資金では、初期仕入+固定費の3~4か月分程度は準備が必要です。